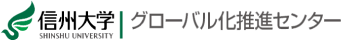チェンマイ留学で見つけた、"こうあるべき"じゃなくてもいい生き方
八木 知夏さん
教育学部 学校教育教員養成課程
留学期間:2023年11月~2024年10月
留学先:チェンマイ大学
留学先大学について
チェンマイ大学は、タイの北部チェンマイにある国立大学です。大学の面積は松本キャンパス×59個分という広大な土地の中に17の学部と107の学科があります。チェンマイ中心部の人口は22万で、そのうち学生、教職員・スタッフなど大学関係者が約6万人を占めます(2024年10月)。授業はタイ語のコースと英語開講のインターナショナルコースがあり、私は社会科学部のインターナショナルコースで勉強しました。学期は6-10月/ 11-3月の2学期制です。1科目当たりの単位数は通常3単位で、一科目当たり週3時間×17週授業時間があります。
私が留学した社会科学部のインターナショナルコースは、一学年あたり約40人の正規学生と数人(5人以下)の交換留学生がいました。授業は「すべての物事は社会的に作られている」という仮定の下、リーディング、ディスカッション、プレゼン、ライティング、フィールドワークなどのタスクなどをこなしながら学習する形式でした。現在は、隣国ミャンマー国内の教育機関が機能していないため、社会科学部のインターナショナルコースのクラスメイトの9割はミャンマー出身でした。(最初は教室の中でタイ語が全く聞こえないのに驚きました。)ミャンマー以外にも、シンガポール、ネパール、中国、タイ、など様々な地域から学びに来ている人がおり、クラスの中でディスカッションすると多様なバックグラウンドを感じることが多く興味深かったです。
学習面について
最初に戸惑ったのは、言語。それぞれの出身国の影響を受ける英語の発音や文法に慣れるのにしばらく(二週間から半年ぐらい)かかりました。わかったことは、とりあえず聞いたことを自分なりにアウトプットしながら聞くことは理解を助けるのに役立つことがあること、間違えることを恐れて話をしないことより間違えてもいいからとりあえず思ったことは言ってみること、わからないことは聞いてみることが大事だということ。また、リーディングやライティング課題の多さにも戸惑いましたが次第にスケジュールやコツをつかむことができたと思います。クラスメイトに課題に取り組むコツなどを教えてもらったのも役に立ったと思います。信大よりもたくさんディスカッションをする場面があり、自分の意見を持ってから授業に臨むことを心掛けました。
グループワークは大多数が毎日課題に追われるぎりっぎりの生活を送っていたので、前日にやることが多かったです。そのペースをつかむまで間に合うのか心配した時もありましたが、つかんでからは前日に自分がやりたいことや言いたいことが言えるように準備をするようになりました。適応、だと思います。
生活について
衣:年中半袖でしたが、室内は極寒の地(特に教室と図書館)だったので羽織るものを持ち歩いていました。長距離列車も寒いです。お寺では露出の多い格好は禁止です。
食:毎日、ご飯や果物を選ぶ&食べる時間が大好きでした。大学の周りには安くておいしい屋台やお店があふれています。ただし、野菜を見つけるのはそんなに簡単ではなかったので、栄養バランスを維持するように気を付けていました。
住:大学の門から5分の所にアパートを借りていました。エアコン、あったかい(ぬるい)シャワー、気分屋のWi-Fi、やもりと一緒に住んでいました。追加設備として扇風機と大気汚染対策の空気清浄機、炊飯器とIHクッカー(部屋に台所無)に投資しましたが、とても良い仕事をしていたので全く悔いはありません。特に扇風機はヘアドライヤー、衣類乾燥機、扇風機の三役を一人でこなしていました。あるだけでQOLが上がること間違いなしです。(帰国するときには友達に譲りました。)
交通:チェンマイは公共交通機関が無いに等しい場所です。
出かける時は
・人が多い場所に行くなら:ソンテウという乗り合いバス(というかトラックの荷台にベンチを置いたもの)を見つけて交渉し乗る(たいてい一人30バーツ)
・徒歩三時間以内の人があまり行かない場所に行くなら:inDrive というアプリでバイクタクシーを呼ぶ。幸運を祈って乗る。私はバイクを使う機会が多かったので、お守りを買うような気持ちで日本製のヘルメットを中古で買いました。
・それ以上の距離の場所に行くなら:長距離バスか列車に乗る
☆バンコクまで寝台列車で12時間ほど。私はとっても楽しかったですが、快適に乗るには時間がかかる人もいるみたい。勇気がある人はぜひ。ちなみに、行こうと思えばマレーシア/シンガポール、カンボジア、ラオスまで電車で行くこともできます。

留学で得たこと
一年間の留学を選んで、変わったと思うことを書いてみます。
精神面:
・なんでも、なるようになると思うこと
ไม่เป็นไร まいぺんらい、という言葉は魔法の言葉だと思います。
・こうするべき、やこうしなければいけない、と思うことが減ったこと
➤集まる人々のバックグラウンドが多様になればなるほど、「こうあるべき」という考えが「こういうのもあり」と変化していきました。その変化のおかげで、少し生きるのが楽になった気がします。
・自分は自分のためにしか動けないと考えるようになったこと
➤誰かのため、と思って何かをしていたとしても、それは結局誰かのためになりたい自分のためなのでは?と。発展とか開発について学んだり、日常生活で人と関わったりする中でそう感じるようになりました。
だけど、それが結果的にだれかにとってうれしいと思うことだったりもする。ややこしいからこそ、人と関わることが面白くなったかもしれません。
学習面:
・一年間でかなりの本数の論文や文献を読み、プレゼンやディスカッションを行った結果語彙力や英文を処理する速度・制度が上がった。
➤アクセスできる情報の量と質が変化した気がします。学術的な意見を知りたいと思ったことに関し気楽に論文検索できる。文献検索、引用、文章構成などを改めて学んだことは、物事を論じる技術の向上につながっているかも。
・様々なイントネーションを含む英語に適応するプロセスに慣れた。
➤時間はかかるけど、時間をかければ分かるようになるということを学びました。
生活面:
・体調管理のための早寝早起きと食事の大事さを実感
➤精神的にも身体的にも健康を保つことは、様々なことに取り組む基礎になると思います。基本的な生活習慣をこれからも大事にしたいです。
社会科学を学んだ結果、教育や社会の中の物事、社会に生息する人の見方が変わったと思います。すべての物事は社会的に作られているということ、様々な、と言っても様々という言葉に収まらないぐらい人のバックグラウンドにある文化や前提は異なること、同じ言葉を聞いても人によって連想するものは違うこと。生きるのはとんでもなく難しくて複雑で、だから面白いです。
後輩へのアドバイス
交換留学に行こうと決めたとき、ちょうど募集の締め切り一週間前でした。かなりバタバタと申請書を書いたり、奨学金について調べたり、あわただしかったと思います。この経験から学んだことは、ギリギリでもなんとかなることがあること、行きたいと少しでも思ったら申し込んでみることの大切さ、もしも、少しでも留学に興味があるなら早い目に英語の試験は何か受けておいても損はしないのでは、ということです。
あとは、時間との距離感。信大と留学先大学の時間との距離感(のんびり度合い)はおそらく違います。時間との距離感に差があると、準備が思うように進まないことがありますが、そういうものだと思ってたくさん交渉しましょう。私の場合は、受け入れやビザに関する書類が全てギリギリで、タイ語を話せる知り合いに頼んで催促の文章を書いてもらいました。渡航後に向こうの時間に適応することはそんなに難しくありませんが、日本にいる時は日本の時間との距離感を無視できないことがあります。良いバランスを見つけられることを祈ります。